Content Marketing World 2013 in オハイオ 参加報告
こんにちは。プロデューサーの塩崎です。
2013年9月10日と11日にオハイオ州にて開催された、Content Marketing Institute 主催のイベント『Content Marketing World 2013』に参加してきました。
Content Marketing World 2013 公式イベントサイト
※既に来年2014年の告知サイトになっていますが、2013年のアジェンダも2013年10月7日現在、見ることができますのでご興味のある方はぜひご参照ください。
今回は、40か国を超える国々から1,700人ほどが参加したようです。

そもそも、Content Marketing という言葉が意味するものですが、私個人の見解としては、ソーシャルメディアや、メディアの細分化・多様化が非常に進み、顧客が接する1コンテンツあたりの消費時間が短くなり、旧来の手法だけではメッセージが伝わりづらくなっている現代において、更に何ができるのかをコンテンツ側面から考える手法のことだと捉えています。
(「コンテンツ」という言葉は、一般的にはテキスト+画像+動画自体とそれを用いて伝達するものを指しているそうなので、Content Marketing の分野で使われる content という表現は、「ブランド・メッセージ・コンテンツ」くらいの方が、日本語訳としては正しいと思っています)
セッションは、
B2B, B2C, CONTENTS STRATEGY, SEARCH&SOCIAL, CONTENT CREATION,
MULTI-CHANNEL CONTENT, CONTENT INTEGRATION, SOCIAL MEDIA, CONTENT DISCOVERY
の各カテゴリに分かれ、2日にわたりパラレルセッションで展開されました。

今回、私が参加した背景としては、以前IAサミットで出ていたコンテンツストラテジーの考え方が、より実戦でどのようにエージェンシーが対応しているか、プロジェクトにおいて、どのようなプレーヤーが、どのようなサービスを利用してサービスを提供しているかを中心に探りたい、という考えがありました。
Content Marketing はまだまだ発展中の考え方ではあるので、どんどん情報交換をしていきましょうというスタンスで非常に成長感が感じられる現場でした。登壇したスピーカーも、他のスピーカーの話から熱心に学んでいるそうです。
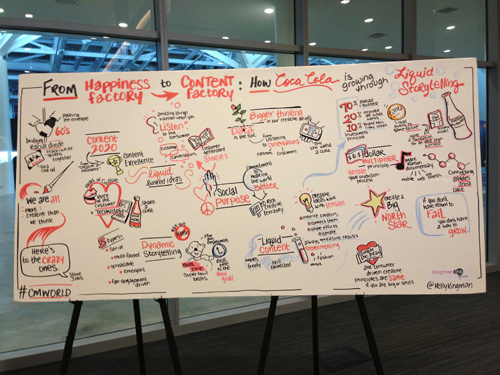
印象に残ったキーノートとセッションを1つずつ要約してご紹介します。いずれもContent Marketingの必要性について語られていました。
《Keynote:Why Smart Marketing is about Help not Hype/Jay Baer》
(『詐欺ではない、スマートなマーケティングはなぜ助けになるのか?』)
□トピック
●情報ソースが爆発的に増加している
ブログの数3500万サイト(2006年)→1億7300万サイト(2011年)
●3つのタイプの情報発信ツールが必要(3つのタイプのユーテリティー)
1、自分で情報を取りに行くもの
・必要となる情報量は激増している。購入前の情報取得ソース数5.3(2010)→10.4(2011)
・スマホが出てきたおかげで、適切な判断をしようとするときに出先でスマホを使わないと、情報取得行動の手抜きとも思える
・関係性は人が作るのではなく、情報が作るもの
・B2Bの顧客は70%の意思決定が完了した後にしか、セールスレップに連絡をしない
2、徹底的な透明性のあるもの
・マクドナルドのFAQに、「牛をどのように飼っているのですか」という質問が上がったのに対して、マックは農場に行って農家に質問をするコンテンツを作った。
・どうやって売るかを考える前に、どのようにうまく伝えるかを考える方が良い
3、リアルタイムなつながりのあるもの
・物語を大きくする(ストーリーで伝える)許可を自分に与える
・ヒルトンが、Q&Aサービスのようなものを始めたり、見込み顧客をどのように惹きつけるか等を考えている。そもそも見込み顧客というよりは、「自社の顧客セグメントが何に興味をもっているのか」に着目している。
例:コロンビアはロープを売っていないが、ロープの結び方のインフォメーションサイトを持っている事例もある。
□まとめ
情報の増加に伴い、顧客の購買前の情報収集行動に企業は協力して行く必要がある。その際には、狩人ではなく、農家の発想(捕らえるのではなく、育てる)で情報提供が必要。顧客の情報取得のステージに合わせて自社の運用体制を考慮し、継続的なコミュニケーションが必要。
なお、スピーカー Jay Baer の著書でこのキーノートと同タイトルの著書がありますので、興味をもたれた方は読んでみてください。
『Youtility: Why Smart Marketing Is about Help Not Hype』(Jay Baer 著書)
《Session:Building Your Content Strategy around Shared Purpose(Advanced)/Mark Bonchek, ORBIT+Co》
(『目的をシェアするためのコンテンツストラテジーの立て方』)
□トピック
●ベストのコンテンツは、顧客のために作っているのではなく、顧客とともに作っているものである。
●ブランドプロミスとブランドパーパス
・ブランドプロミス
ブランドが約束するもの
なぜ商品を信じられるか
商品を買う理由
トランザクションから得るもの
企業がやっていること
・ブランドパーパス
ブランドがしたいと思っていること
なぜ企業を信じられるか
信じるための理由
関係性から得るもの
企業がある姿
→パーパスはプロミスに隠れている「なぜ」の部分
ウォルマートの事例
always low prices → save money:Live betterにタグラインを変更
●ブランドの役割が、『説得・約束』から『つながる・共に作り上げる』に変わり始めている
□まとめ
ブランドやコンテンツの役割は変わり始めている。それに対応している企業も現れ始めている中で、変化を起こすか起こさないかは、その企業の姿勢自体を顧客に見せてしまいかねない。
難しいところからやるのではなく、シンプルなところからスタートするのがベター。動画だけ、スペシャルコンテンツ等、やり方はいろいろありそう。
《所感》
この他にもいろんなセッションに参加してきました。所感を以下にまとめます。
現在、自社の商品やサービスのマーケティング施策を考える際、考慮すべきポイント(=メディア)の複雑化が始まり、より視野を広げる必要があるところまでは理解している企業は多いと思われます。ただ、従来と同じことをやっているだけでは、顧客は意思決定した後にしか自社のメディアに接触せず、企業側が新たな打ち手を考え行動に移さなければ、意思決定までの過程に働きかけることはできなくなってきている。
例えば、昔は雑誌に載っていたものを買っていた顧客が、価格コムとメーカーのサイトで商品を見て買うようになり、遂には、Facebookのタイムラインに流れたものを、周りの評判を集めて価格コム経由で購入するようになった。
メーカー側はこれにどうやって対応すればいいのでしょうか?
従来の方法も当然大事ではあるものの、さらに+αの手法も検討しないと対応できない。
見込み顧客が誰で、どのようなニーズをもっているのか、より深掘りしないといけない時代になってきた。
所感として感じたことは以上ですが、同時に、Content Marketingのトレンド・手法だけでは問題解決が図れず、HCD(人間中心設計)をベースにした、ブランディング/マーケティング/PR等とのさらなる連携が必要なのだと思いました。
ユーザの把握と、資産(コンテンツ)の把握、そしてそれらを利用したアイデアの精度を上げるために何ができるか。
『Content Marketing World 2013』の各セッションで紹介されていた考え方は、学ぶところがかなり多かったです。今回得た知見をもとに実践を繰り返し、コンセントが提供するサービスの強化を図っていきます。