新人デザイナーの可能性をひらく書籍対談(6)『言語の本質』編
- サービスデザイン
- UX/UIデザイン
- コンセントカルチャー
コンセントの代表取締役社長の長谷川敦士と新卒1年目社員が1冊の本をテーマに対談。本から得られた気付きを通して、それぞれのデザイン観やデザインへの思いを語り合います。

長谷川敦士(写真左)
代表取締役社長/インフォメーションアーキテクト
東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。「わかりやすさのデザイン」であるインフォメーションアーキテクチャ分野の第一人者。2002年に株式会社コンセントを設立。企業ウェブサイトの設計やサービス開発などを通じて、デザインの社会活用、デザイン自体の可能性の探索を行っている。
竹村明奈(写真右)
デザイナー
武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業。グラフィックデザインを主軸に、紙媒体、ウェブ、ブランディング、プロダクトデザインなど幅広い分野で制作を行う。2023年、コンセントに新卒入社。主にサービスのUX設計やアプリケーションのUI設計に携わる。
書籍紹介
『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』今井むつみ/秋田喜美 著|2023年5月刊行|中央公論新社出版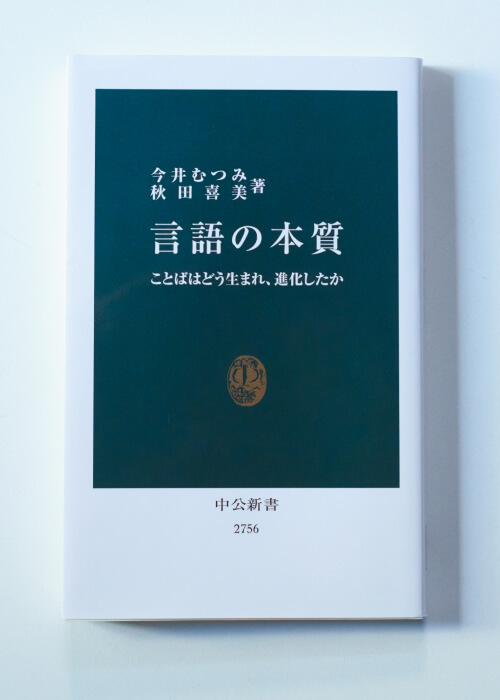
出典:中央公論新社「中公新書|言語の本質」
(閲覧日:2024年2月14日)
1. 言葉の始まり、オノマトペ
長谷川:僕は以前から言葉の発生について興味があり、いくつかの本を読んで、その中から今回の推薦図書としてこの本を選びました。この本で、言語習得の始まりはオノマトペ*1から、という話があります。その内容について竹村さんはどう思いましたか?
*1 オノマトペ:音や声、状態などを言葉で表現した言葉。擬音語と擬態語の総称で、英語ではonomatopoeiaと表記する。
竹村:もともと言語や子どもの成長に興味があったので、推薦書の中でも特にこの本のテーマに興味がわきました。オノマトペから始まる言語習得のプロセスというのは、とても面白い視点だと感じました。
長谷川:そうですよね。オノマトペは、見方を変えると幼稚な表現に感じられることがあります。でも実際には、言語習得の鍵となっている。だからこの本では、オノマトペは「言語」であると強く主張されていて、その点が非常に興味深い。
竹村:オノマトペは、言語習得においてチュートリアルのような役割を果たしているのではないかと思いました。本の中で「言葉には身体性がある」という内容もありましたよね。私は学生時代から子ども向けのワークショップ運営に取り組んでいるのですが、そこでの経験を思い出しました。
子どもたちとの会話でオノマトペを使うと、グッと伝わりやすくなり、子どもたちの理解度が高まるように感じることがあります。例えば、何かの動作をしてほしい時にオノマトペを使うと、その表現に動きがリンクして、自然と身体を大きく使ってくれるようになったり。

長谷川:なるほど。そのエピソードは、オノマトペが「頭での理解」と「身体での動作」との橋渡しになっている点が面白いですね。
竹村:はい。子どもたちの語彙力は、大人と比べるとまだ十分ではありません。でもオノマトペを使って会話していくうちに、自然と言葉の意味を身体を使って覚えていくプロセスを目の当たりにしました。
2. 理解と感覚。そのバランスをデザインする
長谷川:オノマトペというのは、意味自体を伝えるよりも感覚的にわかるという点で、効果を発揮しますよね。実はその効果というのは、デザインでも生きてくる部分があると思っています。
竹村:デザインに生きる言葉の効果ですか?詳しくお聞きしたいです。
長谷川:私たちが普段デザインする上では、ある程度ロジックが必要になります。特に、エディトリアルやデザインシステムといったデザインする対象の規模が大きくなると、ロジックの活用やルール化をせざるを得ません。
でも、ゴリゴリにロジックだけでものづくりをしてもまったくエモさが感じられず、面白みがなくなることもあります。それでは結果として、ユーザーに受け入れられなくなってしまう可能性もある。それは避けたいですよね。

竹村:はい。情報構造化やトーン&マナーなど、デザインにおいて伝わりやすくするルールはもつべきだと、理解はできます。でも無機質に整理されるだけだと、確かに違和感も覚えますね。
長谷川:そういった時、どうすれば望ましいコミュニケーションを生むことができるのか。デザインする上では、そこも考慮すべき範疇です。そこで大事な要素の一つとなるのが、言語表現だと思います。
どんなに大規模なデザインシステムやメディア媒体であっても、人々が触れる部分は、グラフィックや文章で表現されます。だから言葉遣いの微細なニュアンスが、そのデザインやグラフィックの質を決定付ける一要因になることもありますね。
竹村:確かにそうですね。それはつまり、語彙力が豊富な大人であっても、言語が指す意味だけで理解しているのではなくて、より感覚的な要素で理解が補われることでコミュニケーションが成り立っているのかもしれない。そんなふうに受け取れます。これからいろんなデザインに取り組む上で、見落としたくない観点だと思いました。
3. 失敗こそ学びの本質。だから怖くない
長谷川:この本でもう一つ重要な話題として、アブダクション*2によって人間が意味を獲得していくという話があります。デザインを考える時の中核になりうるアブダクションの話題が、言語の世界にも登場する。ここも言語とデザインの共通点ですよね。
*2 アブダクション:遡及推論(リトロダクション)とも呼ばれる、結果から遡って原因を推測する論理のこと。
アブダクションは「新しい仮説」を導き出す。たとえば、内陸の地域で魚の化石が見つかったとする。そのとき、その地域はかつては海であったという仮説を導くことができる。こういった仮説形成の思考がアブダクションとなる。このとき、この「仮説」は一つではなく複数想定することができる。また、仮説にどういったものを設定するかは推論者の発想力(想像力)に依るという特徴がある。
引用:株式会社コンセント「サービスデザインとアブダクションの思考 イノベーションのためのサービスデザイン(13)」
竹村:はい。コラムにあった「子どもの言い間違い」の話は印象的でした。そのコラムでは、言い間違いの中から言葉を分析して、そこから得た複数の知識を組み合わせて新たな言葉を創造するという知識の創造プロセスが導き出されていました。
長谷川:多分、それがこの本の本質みたいなところですね。
例えば、プログラミングをやる際に一番学びになるのは、プログラムを書いてみてうまく動かない時なんです。エラーが出て、それが何のエラーなのかわからない時ってありますよね。だからその要因を調べてみる、という過程が発生する。その「なぜ間違ったのかを探る」という過程こそが学びになります。
このプログラミングの話も子どもの言い間違いと同じで、学び方や学習観についての新しいヒントになるのではないかと思います。
竹村:なるほど、体験を繰り返すうちに自然に身に付いていく。それが学習の本来の形なのかもしれませんね。
長谷川:さらにこの本が示しているのは、失敗を修正し続けて、一歩ずつ進んでいくことの大切さですよね。たとえ学問として勉強したわけではなくても、失敗と修正を通じて言語は習得することができる。これは、キャリアや年齢にかかわらず学び続けることが提唱される現代社会で、とても勇気づけられるメッセージだと思います。

竹村:その失敗と修正は無意識のうちに行われていると考えると、人にはもともと学習することの潜在能力が備わっているということですね。自分にもその能力があるのだと思うと、これから多少失敗を経験したとしても、それがヒントになるのだと思えて怖さも軽減するような気がします。
4. もっと意図的に、試行錯誤
竹村:プログラミングのエラー解消も、言い間違いから言葉を覚えていく過程も、仮説を立てて行動し、修正を繰り返すデザインの過程と共通しているなと感じました。デザインの仕事でも、単に頭の中で考えるだけではなく、同時に手を動かしながらいったんラフにでも形にしていくことで、具体的な課題や論点が見えてきますよね。
長谷川:そうですね。デザインのプロセスの中で、アブダクションは必要不可欠です。僕は、アブダクションを発動して学んでいくことをもっと広める必要があると感じています。デザイナーの学習過程においても、アブダクションを活用できるような環境整備が必要です。つまり、ただ正解へ導くだけでなく、学ぶ人が試行錯誤できる環境づくりをするということです。
ちなみに竹村さんの学習環境はいかがでしたか?在籍していた大学では、アブダクションを活用した学びがあったでしょうか。
竹村:アブダクションという言葉自体は使われていませんでしたが、それに近い教えは受けていました。
長谷川:なるほど。僕は竹村さんの今の認識のように、経験則から感覚的にわかっていることでも、あらためて「それはアブダクションだ」と、きちんと言語化することが重要だと思っています。
ユーザーが自分なりに試行錯誤できるもの、あるいは状態を、僕たちはどうデザインできるのだろうか。ユーザーが自分で考える意欲を失わないようなデザインについて、結構考えていますね。
竹村:試行錯誤できる環境を整えるために、意識的に言語化してデザインすることで、人が学習する潜在能力を最大限に引き出すということでしょうか。デザインがもつ可能性がさらに広がった気がします。

5. 対談を終えて
『言語の本質』を通して、言語や人の言語習得プロセスについて理解すると同時に、言語という複雑であり、当たり前に備わっていると思っていた存在を解明していくことで、言語とのつながりや人の学習・創造プロセスが明らかになりました。一つのテーマを深掘りすることで、さまざまな疑問が生まれ、他の事柄と結びつけることで考えが拡充していくのを今回、実感しました。あとがきでも、「筆者の思考の道筋がアブダクション推論である」とあったように、この対談自体もアブダクション推論であったと感じました。

写真/今井駿介
- テーマ :











