成長するデザイナーの特徴とは? 8名のデザイナーの体験談から見えたこと 〜勉強会「丹青社×コンセント 異業種デザイナーと考えるデザインの拡張」レポート
- サービスデザイン
- UX/UIデザイン
- コミュニケーションデザイン
- 教育・人材育成
近年、デザインの役割は急速に拡大しています。私たちデザイナーには、自身のデザイン観を柔軟にアップデートし、従来の領域を超えた視点が求められています。このような変化の中で、デザイナーはどのようにして成長の機会を見いだせるでしょうか。
そんな課題感を背景に、「異業種デザイナーと考えるデザインの拡張」をテーマとした勉強会を、株式会社丹青社(以下、丹青社)とコンセントで2024年11月に開催しました。

丹青社は商業施設や文化施設、ホテル、医療施設、イベントなどの企画からデザイン、施工、演出、運営まで、お客様のニーズに合わせて手がける空間づくりのプロフェッショナル。一方のコンセントは組織や事業、顧客体験やその接点などをデザインする会社です。この勉強会は、異なった領域で活動するデザイナーが互いの知見や経験を持ち寄り交流することで、デザインの拡張や成長(アップデート)について考える場を創出したいという思いをきっかけに、丹青社のデザイン戦略室とコンセントのOrganization Design groupの対話から生まれた探求の場です。
勉強会では両社から、空間デザイン、サービスデザイン、人材開発・組織開発という異なる分野で活躍する8名のデザイナーが登壇し、「わたしのアップデート」をテーマにデザインの拡張とキャリア構築の道のりについて共有し合いました。
本記事では異業種デザイナーとの対話から得た、デザインの拡張のために欠かせない「成長」に関する気づきを共有します。現在はUX/UIデザイナー、デザインストラテジストとして活動していますが、過去にはフローリングや壁紙などの建築建材のデザインも経験している私、叶丸恵理も登壇者として参加しました。登壇者と聴講者、双方の視点から紹介します。

丹青社、コンセント 登壇者8名
デザイナーの成長に共通する3つの要素とは?
8名のデザイナーの具体的な経験から、デザイナーのキャリア開発における、スキルや態度、マインドのアップデートには下記のような共通点があることが見えてきました。
- 自身の活動領域を積極的に拡張し、新しい分野に果敢に挑戦し続ける
- 既存の専門知識を新たな場面で効果的に活用し、キャリアを発展させる
- 戦略的なパートナーとしての役割を担うことを目指す
分野は異なっていても、本質的な課題に取り組む過程で、必然的に自らの領域を拡張していく姿が印象的でした。
成長のための具体的アプローチ
では、デザイナーとしての成長にはどのようなアプローチが効果的でしょうか。登壇者の印象的なエピソードを通じて、その糸口を探っていきます。
ピンチを転換点として活用する
皆さんは困難な状況に直面したとき、それをどのように受け止めているでしょうか。
環境の変化や制約を「キャリアの転換点」として前向きに活用することの大切さを、丹青社のチーフクリエイティブディレクター安元直紀さんの経験から学ぶことができました。

丹青社 デザインセンター チーフクリエイティブディレクター 安元直紀さん
安元さんは初めてワークプレイスデザインを担当した際、社内に経験されている先輩がいない状況に直面したそうです。しかし、その状況を前向きに受け止め、自ら情報を集め、外部のデザイナーから学び、自身の商環境デザインの経験を生かすことで、新たな価値を生み出すことができました。「ピンチに直面したときは、いずれの場合でも試行錯誤が必要になります。しかし、そこから自分なりのブレイクスルーが生まれてくるのではないでしょうか」と安元さんは語り、変化や制約を成長の機会として捉えることの大切さを強調しました。
お話を聞いていて思ったのは、私自身も成長を実感したのはピンチの場面だったということです。チームマネージャーへの転換期には、初めての経験に自信を失いかけましたが、周囲からのフィードバックを積極的に取り入れ、自分らしいマネジメントスタイルを見いだそうと気持ちを切り替えたことで成長につながりました。これについては当日の登壇でもお話ししました。

コンセント UX/UIデザイナー/デザインストラテジスト 叶丸恵理
また、コンセントのサービスデザイナー川原田大地からはアップデートに向けた心持ちについて、「自分ではコントロールできない出来事は必ず起こるものです。病気や事故、災害など、さまざまなことが起こり得ますが、どんな経験も学びになると信じているので、経験を学習として捉え、新しいチャレンジも全て実験として前向きに取り組んでいきたいと考えています。そのためにも、好奇心の火を絶やさないようにしていきたいです」とありました。どんな状況でも学びの機会として捉え、成長し続ける思いに私も深く共感しました。

コンセント サービスデザイナー 川原田大地
自ら領域を広げていく
デザイナーの領域拡張に向けては、どのような取り組みや姿勢が重要なのでしょうか。
コンセントのサービスデザイナー岡本 亮は、エディトリアルデザイナーからサービスデザイナーへと転身した経験を振り返りました。
当時、エディトリアルデザインで培った紙媒体での情報整理力が、異分野の事業開発プロジェクトでも活用できると気づき、サービスデザインの領域に挑戦。「プロトタイプ制作において、エディトリアルデザインの経験が強みとなった」と語り、架空のサービスのユーザーテストでは、リアリティのあるパンフレットを制作することで効果的な評価につながったそうです。

コンセント サービスデザイナー 岡本 亮
「情報整理の考え方をユーザー分析に生かせた」とも話し、エディトリアルデザイン時代に磨いた情報整理のスキルを、ユーザーインタビューの分析やカスタマージャーニーマップの作成に応用。これにより、ユーザーの本質的な考えを見いだせる分析力を発揮することができました。この経験を通じて、岡本は「マインドセットを変えていく、スキルのアップデートの重要性」を認識。既存のスキルを生かすことを大切にしながら、自分にできることを地道にチャレンジし、試していくという姿勢で、新たな価値創造に取り組んでいるそうです。
また、丹青社のシニアクリエイティブエキスパート那須野純一さんからの、「時間効率が重視される現代においても、あえて『余計なこと』に取り組んできた」というお話が印象的でした。これは単なる付加的な活動ではなく、事業の本質的な成功につながる重要な要素だと思ったからです。
具体的には、工事現場でのプロモーションの仕掛けやキャラクターデザイン、商品開発、さらには施設にまつわる物語設定の執筆まで、空間デザインの枠を大きく超えた多様な取り組みを展開されてきたそうです。那須野さんは「純粋な空間デザインだけでは、お店の集客や成功につながらない」という若い頃の気づきから、「デザインの枠を超えて、事業成功のためにさまざまなアプローチを試みる姿勢を貫いている」と語りました。

丹青社 デザインセンター シニアクリエイティブエキスパート 那須野純一さん
コンセントでも同様に、先を見据えた提案ができるよう、継続的なアップデートを行ってきました。エディトリアルデザイナーからサービスデザイナーとなり、役員も務めるコンセントの大﨑 優は「経営視点からデザインの価値を捉え直し、ビジネスへの理解を深めながら、事業におけるデザインの意味を追求することで、デザインの役割を拡大させてきた」と語りました。両社に共通するのは、与えられた範囲にとどまらず、事業の本質的な成功に向けて、自発的に価値提供の領域を広げていく姿勢です。
これまでの専門知識を生かしつつ、自発的に提案の範囲を広げ、新たな価値を生み出し、クライアントとより深い関係を築いていくことの重要性を実感しました。

コンセント 取締役/デザインストラテジスト/サービスデザイナー 大﨑 優
戦略的なパートナーの役割とファンづくり
クライアントとの関係構築とデザイナーとしての姿勢の変化は、私たちの成長にどのような影響を与えているのでしょうか。
両社の共通点として浮かび上がったのは、制作者の立場を超え、戦略的パートナーとしての役割の確立に向けて積極的に取り組んでいた点です。丹青社のデザイナーが語った「クリエイターとしての独自性」についての考察をご紹介したいと思います。
丹青社のクリエイティブディレクター眞田章太郎さんのお話で印象的だったのは、内装設計・施工の依頼から始まったプロジェクトが「ブランディングを求められる仕事へと発展していった」ことです。限られた予算の中で工夫を重ね、それがデザインの突破口となり、空間にボリューム感をもたせることに成功しました。この経験がお客様から「デザインっていいね」という反応を引き出し、クライアントに新しい気づきを与えることができたそうです。お客様と一緒にサービスの価値を育てていく過程で、世の中に話題性のあるプロジェクトを生み出すことにも成功。次第に意見を求められる存在へと変化し、ブランディングについても相談を受ける深い信頼関係を築くまでになりました。

丹青社 デザインセンター クリエイティブディレクター 眞田章太郎さん
眞田さんは、「良い空間をつくり、ブランディングを成功させ、クライアントのビジネスの起爆剤となり、双方の利益を確保してビジネスパートナーとしてwin-winの関係を築くこと。これはデザイナーとして当たり前のベースとなる部分です。では、その先の自分のアップデートはどうあるべきか。より上流工程に立ち、発言力を高めることが次のステップだと考えています。発言力を高めることで、単なるデザイナーから意見を求められるデザイナーへと変化しました。お客様から『どう思いますか?』と相談される立場になってきたんです。これにより、やみくもに疲弊するまでデザインに没頭するのではなく、より高い視点で仕事ができるようになりました。逆算的に考えると、デザインは私たちの仕事の軸足ではありますが、それはゴールではありません。結果として発言力を高めていくことが、私の考えるアップデートの方向性だと思う」と語りました。
さらに、眞田さんは写真家としての活動を通じて視野も広げているそうです。「何が突破口になるかわからない、どんな相談が来るかわからない状況では、デザインだけでなく、さまざまなジャンルに精通することが重要です。空間デザイナーという肩書にとどまらず、一人の『クリエイター』として多様なスキルを磨き、準備しておくことが、自身のアップデートとして大切だと考えている」とお話しされていました。
また、丹青社のクリエイティブディレクター鶴岡信人さんは、戦略的パートナーとしての関係構築やファンづくりについて紹介されました。鶴岡さんは「空間をつくっていく仕事が主なのですが、空間を取り巻く体験やブランディングの部分を包括的に提案していくことで、顧客価値や顧客体験を高めることができる」と語りました。そのため、空間デザインだけでなく、一貫したブランディングのためパッケージやショッパー部分のデザインもさせていただけないかと、デザイナーから提案したそうです。ブランディングへの包括的な関わりを通じて、制作者としての立場を超えた関係性を構築していく過程について、具体的な事例とともに紹介いただきました。
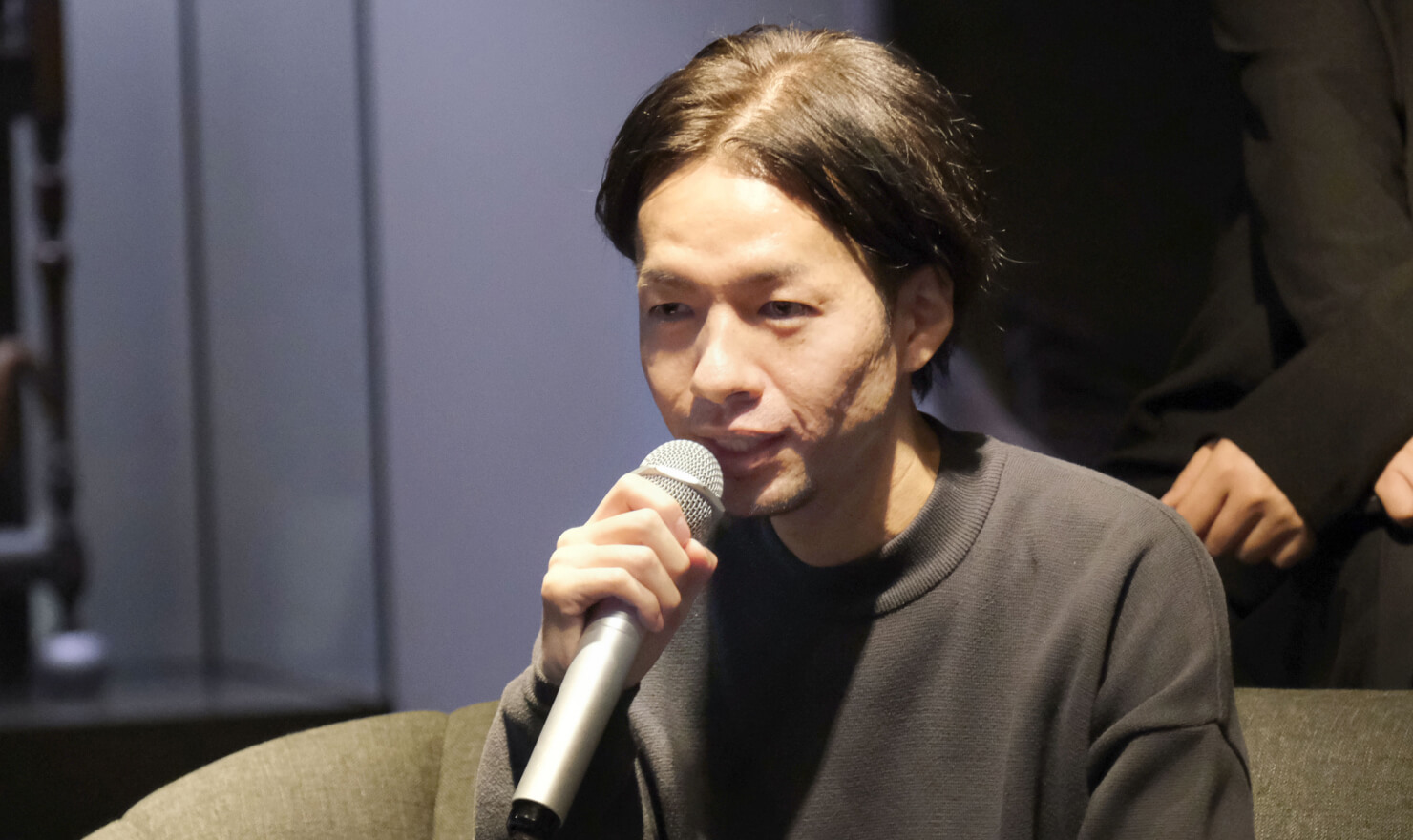
丹青社 デザインセンター クリエイティブディレクター 鶴岡信人さん
さらに、クリエイターとしての独自性について、「組織に埋没せずに、クライアントからの理解を得ながら仕事を進めていくことが大切」と話し、「もし自分が個人で活動するとしたらどうするか、『クリエイター』として個人で仕事をしていく場合にどういったアクションを起こすべきか」を常に意識することの重要性を強調されていました。その結果として、「私の仕事人生で初めて『自分のファン』ができたと感じた」と語り、お互いの主張を交わしながら良好な関係性を築くことができたプロジェクトを共有いただきました。
お二人の話に共通していた「自分のファンになってもらう」という視点は、私も大切にしているものです。この態度は、デザインの領域に限らず、デザイナーの成長と可能性の拡張において重要だとあらためて感じました。

それぞれの発表の後に行われたパネルディスカッションの様子
まとめ
今回の勉強会では、領域の異なるデザイナーがそれぞれ自己成長のために奮闘してきたエピソードがとても印象的でした。勉強会には丹青社とコンセントから、デザイナーをはじめ他職種のメンバー100名ほどが参加したのですが、下記のような感想もあり、大変好評なものとなりました。
- 他社の方の話は新鮮。自社のメンバーでも知らない一面を知ることができた。今回の「デザインの拡張」とは、生きるためのキャリアの拡張だったのだなと感じました。
- 分野は違えども、ものを考えつくっていくというデザイン・プランニングを担う人たちならではの、根底に通ずるものが垣間見えた。それぞれの課題意識や自己成長のプロセスにも共感を覚えたのは、興味深かった。
- 置かれた環境の中で最適解を見つけていく難しさを、楽しみながら追求していることが何よりも強さであると感じました。
ここまで「デザイナーのアップデート」をテーマにご紹介してきましたが、成長には不安や困難な状況がつきものです。多くの登壇者が「心地よい不安」とともに新しい分野に飛び込んでいった経験を語ってくれました。
デザイナーの成長には、未知の境界に立ち、果敢にチャレンジしていく勇気が必要です。不安を伴いますが、その先には必ず新しい景色が待っています。時には意図的に自分を挑戦的な状況に置くことで、想像を超える成長と可能性を発見することもできます。そして、デザインを通じて関わる人々と、未来を見据えた真摯な姿勢を持ち続けることも大切だと感じました。

イベント当日の会場の様子
実は勉強会後のとある週末、品川区の戸越公園内にある環境学習交流施設「エコルとごし」を訪れました。建物の中に入ると、木材のぬくもりと柔らかな光が調和した心地よい空間が広がっていました。3階の展示スペースでは、大人も子どもも好奇心のままに展示物に触れ、体を動かし、笑顔で学び合う姿が印象的でした。
この建物の空間デザインは丹青社によるものです。今回の勉強会で、博物館をはじめとした文化空間を手がけるデザイナーやプランナーの方々と出会ったことがきっかけとなり訪れたのですが、空間デザインの工夫が随所に生きており、環境について考えることがこれほど楽しく、わくわくする体験になるとは想像していませんでした。訪れる人との物語を物理的な空間で紡ぎ出す「空間の編集」に魅力を感じて、多くの刺激と気づきを得られる体験でした。
この学びを成長の機会として活用し、今後も異なる分野のデザイナーが交流しながら学び合える機会を企画していきたいです。










